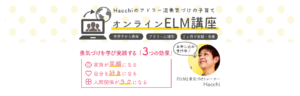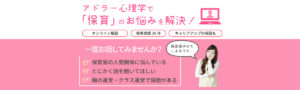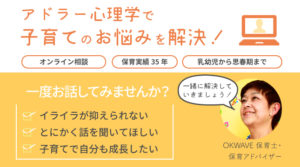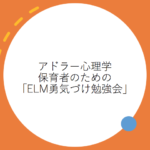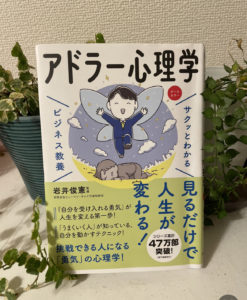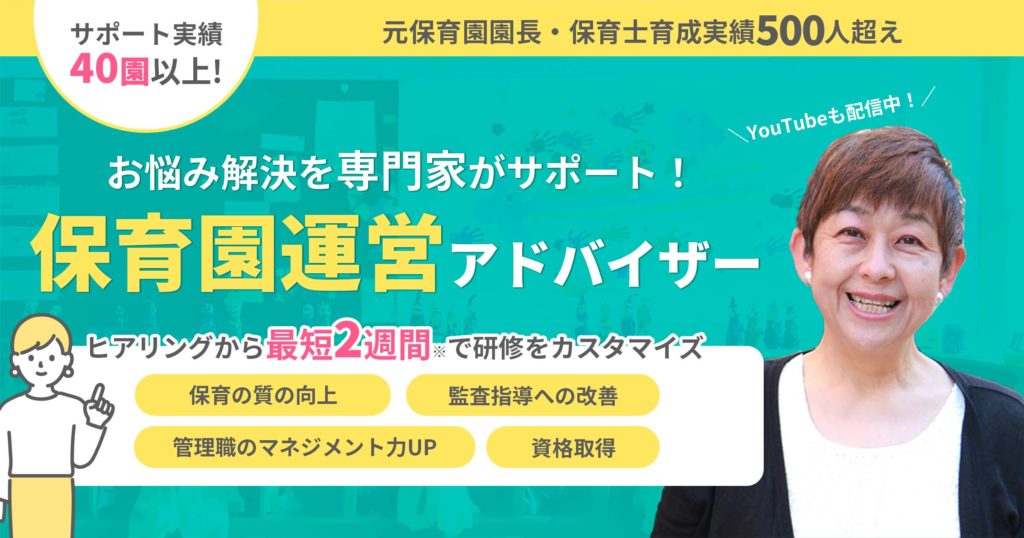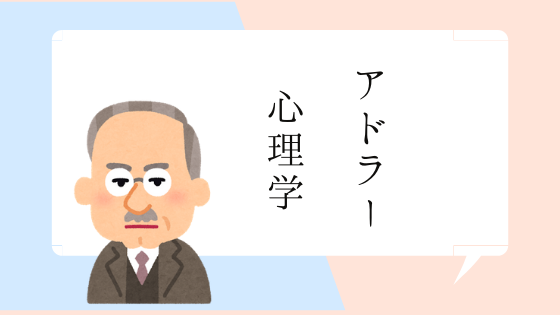
アドラー心理学を学んで人生が変わった!そんな声を聞いてアドラー心理学にご興味をお持ちの方も多くいらしゃるのではないでしょうか? 今回はアドラー心理学の研修の一つELMというコースのトレーナーを務める、弊社のHacchiが「家族・職場・恋愛で役立つアドラー心理学で人間関係を良くするヒント」についてお伝えしたいと思います

目次
アドラー心理学とは
「アドラー心理学」を作ったのは、オーストリアの心理学者、アルフレッド・アドラー(1870-1937)
日本でも岸見一郎氏の「嫌われる勇気」で注目されるようになりました。
「人間の悩みは、すべて対人関係である」
アドラーの言葉に・・・
「人間の悩みは、すべて対人関係である」があります。アドラーは、人間関係の問題を解決するさまざまなメッセージを残しています。
「相手の目で見て、相手の耳で聴き、相手の心で感じる」
この言葉は、アドラーがコミュニケーションでもっとも大切にしていたことです。
アドラー心理学は、理論よりも実践を重視している心理学です。日常生活でやくに立つことを大切にしているのです。
「アドラー流のいい人間関係のコツ」5つの柱
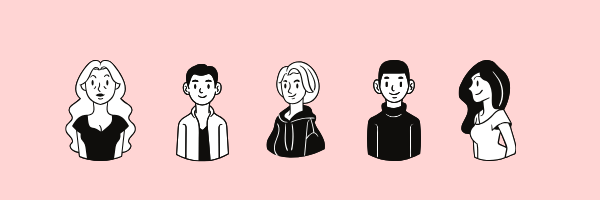
①人生は自分が主人公である(自己決定性)
人は決して、環境や過去の出来事の犠牲者ではなく、自分の行き方を選び、未来を自分で作る自由があります。もし、人と上手くいかないことがあっても、相手がどうにかならないかと思い悩むのではなく、相手への接し方は自分でよりよくしていけるのです。
②人間の行動には、目的がある(目的論)
人が何かをするときにはその人なりに先のことを考えてやっていると捉えます。だからこそ未来は考え方次第でどうにも作っていけるのです。 人間関係で悩む時があっても、過去の原因をあれこれ悩むよりも、前向きに変えられる未来に目を向けて対応していく方が良いのです。
③人間は、心も体も結びついたひとつの存在(全体論)
「心と体」を一体のものと考えます。「人は変わろうと思えばいくらでも変われる」と考えます。人づきあいが得意ではないと感じている繊細な人ほど、相手の気持ちがよくわかり、相手に寄り添うことでいいコミュニケーションが取れるでしょう。
④人間は、自分の主観を通して物事を把握する(認知論)
同じ体験をしても人によって感じ方はさまざまです。いつまでも悩む人もいれば、気にしない人もいます。 私たちの悩みの多くは、事実そのものよりも、それをどう捉えるかによって生じています。自分のものの見方を持っているため、人と分かり合えない、噛み合わないということが起きやすいのです。これを超えて、相手と共感できる、尊敬しあえる、信頼しあえると、人間関係がマルになっていくのです。
⑤人間のあらゆる行動は、対人関係である(対人関係論)
人はいつも特定の誰かを想定して行動している。特定の誰かとは、家族や友人、職場の人、自分などがそれにあたります。行動が向けられる相手との関わり方によって、お互いに影響しあい、人間関係が変わってきます。ですから、相手との関係性によって自分の中のどの面を出すかで、行動や感情が変わり、前向きになっていくのです。

もっと詳しく学びたい!と思われた方は、ぜひアドラー心理学の講座もご活用ください